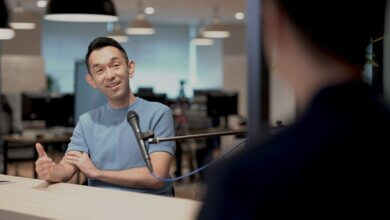Treasure Dataでエバンジェリストを務める若原強が各界注目のゲストを招いて対談する「PLAZMA TALK」。今回のゲストは京都大学総合博物館 准教授であり、日本科学未来館“おや?”っこひろば総合監修、NHK Eテレ「カガクノミカタ」番組制作委員等々、多彩な活動を繰り広げられている塩瀬隆之さんです。
今回は、博物館×デジタルをテーマに塩瀬さんと考えていきます。
塩瀬さんからはまるで博物館の展示のように幅広い分野の話題と、実務に即した深い見識が次から次へと飛び出してきます。
キーワードは「コミュニケーション」です。本対談は3回に分けて配信いたします。
第2回目は、博物館とデジタル化、あるいは「いいとこ取り」の役割分担に関してです。
第1回目のトークはこちらから:
塩瀬さん、「大学博物館」ってそもそもどんなところですか? (ゲスト: 塩瀬隆之さん第1回)
Topics
博物館・美術館のデジタル化論争/デジタルで紹介すると来館者が増える/集客のもうひとつのプロセス/「最後の晩餐」の価値/鑑賞「体験」そのものをオンライン化することはできていない/TaxonomyからFolksonomyへ/民衆は民衆なりの見方があるはず/GoogleのArts & Culture/世界中のゴッホを横串で/地球人の人類資産/without walls/「Googleには日本の文化は検索しきれません」/ネット社会のアクセシビリティ/知っているものはより知られ、知られていないものはより知られなくなる/出会いの偶然性とオンラインの良し悪し/「いいとこ取り」すればええじゃないか/まとめサイトとの違いは「空間を利用できること」/伝えたいことと大きさの表現/来館者の体感の仕方/空間メディアとしての博物館/インクルーシブデザイン/動物のかかとだけ見て回る/目線の違いを視点に/バーチャルリアリティの没入感と「どこを見せるか」/シュートシーンだけじゃないサッカーの見方/視点の選択可能性/双方向のメディア利用
Takayuki Shiose: The Kyoto University Museum/Associate Professor
Tsuyoshi Wakahara: Evangelist, Treasure Data
Recording: 2020/04/14
※収録はオンラインにて行っています。一部背景に環境音が入っている箇所あります。ご了承ください。
博物館・美術館のデジタル化論争
若原 塩瀬さん、今いろいろ展示に関するお話を伺ってきたわけなんですけども、昨今新型コロナウイルスの文脈で、イベントがオンライン化していったり、働く場もテレワーク、在宅勤務、リモートワークみたいに多少変わっていく動きが見られたりとか、リアルで行われていたことがオンライン化していく話も加速しつつあるなと思うんです。私個人的には、前職で働き方の研究もしていた立場からすると、なんでもかんでもオンライン、デジタルっていうわけでも恐らくないんだろうなと。リアルとオンラインの役割分担がもう一度図れるような節目になるんじゃないかなと思っているんです。そういった意味で、博物館とか美術館の展示というものが今後どんなふうに変わっていくのか、塩瀬さん的にはどんな景色をご覧になっているのかなというのを伺ってもよろしいですか?
塩瀬 はい、ありがとうございます。僕自身、さっきの人工知能系の研究とか、ICT、IoT周りの仕事もしていたこともあるので、博物館に最初に異動したときも、博物館っていうのはその場で見るのが一番の体験なので、デジタル化とか、技術好きなやつが来てどうするんだ?みたいな感じで見られたことも実際あるんですよね。なんでもデジタルでコピーすればいいんでしょ?みたいな、そういう目線も確かにあるんですけど、実際に博物館、美術館業界には15年ぐらい前からオンライン化の波というのが一度来ているんです。論争としては1回収束しているんですね。それは何かというと、デジタルで絵を撮ってしまって、WEBにどんどん載せていけば、それで体験として事足りるだろうというのが一つで、もう一つは、いやいやそんなことでは収まらないよ、というのが2つ。やっぱり両論あったんですよね。
デジタルで紹介すると来館者が増える/集客のもうひとつのプロセス
塩瀬 だからどの博物館、美術館も、みんなオンライン化には後ろ向きだったところが多かったんですが、実際にルーブルとか大英博物館もデジタル化に踏み切った部分があって。それは何かというと、デジタルで紹介すると、それで見た人が本当に見たくなって、来館者数が増えるというのが実際に起こったんです。今は集客のもう一つのプロセスとして、実際に絵画とか彫刻を見てもらうというのがムーブメントとしてたくさんあった。なんでかというと、万一スマホとかパソコンで見ても、画面が小さくて、最後の晩餐の価値そのものはわからないんですよね。
若原 確かに鑑賞という意味だとちょっと物足りないですよね。
塩瀬 そうなんですよね。
「最後の晩餐」の価値
鑑賞「体験」そのものをオンライン化することはできていない
塩瀬 だからモチーフとして全部手のひらに乗っかるとか、A4サイズに収まるというのは、そういう構図なんですね、というのはわかるんですけど、ピカソのゲルニカとかも、ダヴィンチの最後の晩餐とかも、あのサイズ、あのスケールで見てこその価値があるわけじゃないですか。そういった意味で言うと、鑑賞体験をそのままオンラインに持ち込むということは実はできていなくて、その構図を体験する、見るということができるだけなんですね。そこで論争の中に節目が一つついたところは、博物館体験のサブとしてであったり、あるいは別の体験として実現できるんじゃないかというのが言われだしたところもあるので、割とオンラインが進んでいったり、アメリカのスミソニアンとかいくつかの美術館、博物館が提携して、Without Wallsというプロジェクトがあって、壁をなくすと。
TaxonomyからFolksonomyへ
民衆は民衆なりの見方があるはず
塩瀬 それぞれの美術館、博物館にあるデータを共有していって、みんなが見れるようになったとき、今までは学芸員の人たちが分類をしていたものを、タクソノミーという、意味を専門家がつけてカテゴリー分けするというところから、フォークソノミーと言って、音楽で言うフォークみたいな感じで、みんなが思っている自分たちの感性から分類をしていくというフォークソノミーのプロジェクトが動き出していて、これとこれが近いとか、これとこれが一緒にいるほうがいいよね、という。民衆は民衆なりの見方というのが本来あるはずと。
若原 それ面白いですね。各博物館という物理的な箱の中に閉じていたものを横串を刺して自分なりにカテゴリーし直せるということですよね。
GoogleのArts & Culture/世界中のゴッホを横串で
塩瀬 そうですね。その究極が、GoogleがやっているサービスでGoogle Arts & Cultureというプロジェクトですね。それは各美術館とか博物館が持っている作品を4Kで撮影をして、デジタルで無料で皆さんが見れるようになっているんですけど、そうすると、例えばゴッホと検索すると、世界中の登録されているゴッホの画像をずらっと並べることができるので、それを年代順に並べると作風の変化が見れたりするので、博物館、美術館一つではできない体験ができるようになる。
地球人の人類資産/without walls
塩瀬 それは地球全体の中の、「地球博物館」からすると、地球人の人類資産をみんなで見れることができるようになると。
若原 なるほど、地球博物館というコンセプトなんですね。
塩瀬 そういう横断ができると。GoogleのGoogle Arts & Cultureというプロジェクトを作ったアーミッド・スードさんという人がいて、Googleが持っている120%ルールの中で、自分が子どもの頃に体験したミュージアム体験がすごく学びとしてよかったので、世界中の子どもたち、アクセスできない子どもたちにそういう体験をさせてあげたいということで、Googleのリソースを使って作ったのがそのGoogle Arts & Cultureというプロジェクトなんです。コンセプトとしても世界中の子どもたちが、人類の叡智にアクセスできるような環境を作りたいということをやっている。
「Googleには日本の文化は検索しきれません」
塩瀬 何年か前に日本版のメイドインジャパンという、Google Arts & Cultureの派生プロジェクトがあって、そのセカンドリリースのとき、僕自身が基調講演でしゃべりに行かせていただく機会があったんです。そのときにGoogleジャパン社長のフィッツジェラルドさん向けに僕がしゃべった内容が、Googleには日本の文化は検索しきれません、という話を紹介したんです。それはなぜかというと、ゴッホとかダヴィンチとか有名な人だと、みんな検索タグのところに入力しますよね。でも例えば日本の伝統文化の中で、小千谷縮とかってあったとき、小千谷縮って外国人知らないので、そもそも検索しないですよね。
ネット社会のアクセシビリティ
知っているものはより知られ、知られていないものはより知られなくなる
塩瀬 だから今のネット社会のアクセシビリティというのは、知っていることをもう一度確認するとか、一度でも聞いたことのあるキーワードからスタートするんですよね。だからまだ出会ったことがないものに出会うという意味で言うとあまり向いていないと。知っているものはより知られ、知られていないものはより知られなくなるというのがオンラインの中でのコミュニケーションの最初のファーストインパクトになるので。だからデータをたくさん入れたからといって、出会う機会がなければ結局埋もれて会えなくなるので、Googleに日本の文化は消化しきれんですわ、というのがそのとき僕がプレゼンさせてもらった内容だったんですね。
そのとき、アミット・スードさんとフィッツジェラルドさんは、そういう挑戦状受けましたけど、とお話をしてくださっていたんです。一応いくつかのプロジェクトがあって、例えばさっきのゴッホを世界中から集めてくるというプロジェクトがある中で、Googleもチャレンジしようとしているのは、それを年代だけで集めてくるとか、色だけで集めてくるとか、モチーフに使われている人物像なのか、動物が写っているのかとか、画像検索を使って集めてくるというのは一応やろうとはしているんだけども、その文化的価値とか意味というところまではまだ付与ができていないと。
出会いの偶然性とオンラインの良し悪し/「いいとこ取り」すればええじゃないか
塩瀬 博物館だからふらっと歩いて、これすごい絵だな、とか、すごいものだな、何だろう?という部分の、出会いの偶然性みたいなところまではまだ作れてないので、オンラインがあればこその体験もあれば、対面、リアルだからこそできる体験もまだ残っているのかなと。その辺がオンラインの良し悪しで、結局両方新しい体験だと思えばいいんですけど、元の生活を死守したい人からすると、奪われるとか、取られるとかってなるのかなと思うので、僕自身は別にオンライン至上主義派でも全くないし、アナログ的な出会い至上主義派でもないので、いいとこ取りすればいいじゃないか、と思っていて。それが余計腹が立つ人もいるのかなと。
若原 でも確かに従来の展示のあり方を守ることが必ずしも目的ではなくて、豊かな学びを得るということを目的にしたとき、おっしゃったいいどこ取りという考え方は僕もすごく共感します。一方で思ったのが、検索で見つけられないものをレコメンデーションしてもらえるみたいな世界って結構いろいろな分野であったりするじゃないですか。その展示とか収蔵物をレコメンドしてもらえるみたいな世界って、同じようにあり得たりするものなんですかね?
まとめサイトとの違いは「空間を利用できること」
塩瀬 まとめサイトが、いわゆるキュレーションと言われるじゃないですか。キュレーションという点からすると近いのかなと思うんですよね。でもそのキュレーティングが、例えば編集、ディレクションというふうにも捉えられるし。キュレーティング活動としては一緒なんですけど、博物館の体験が少し違うなと思うのは、空間を利用できるということなんですよね。スマホのページで見てしまうと、4cm×7cmぐらいの中に縦スクロールで情報がテキストで入ってきたりするじゃないですか。そうすると、上下に並べた時点で、もちろんそこで優先順位ができてくるのと、あとフォントが基本的には同じなので、同じぐらいのボリュームとして受け取られるんですよね。
伝えたいことと大きさの表現
塩瀬 でも例えば、空間で自分を包み込むぐらい大きな空間だと、そこに伝えたいことをどれぐらいの大きさで用意するかによって、その歴史の深さであるとか、大切さみたいなことを伝えることができるので、その空間を使えるというのは大きいことかなと。
来館者の体感の仕方
塩瀬 例えば今展示を準備していてオープンできてないのが一つあるんです。4月8日からオープンの予定だったのが今延期させていただいているんですけど、これはノーベル賞シリーズで、京都大学に山中先生がいらっしゃるので、iPS細胞の研究所の10周年展をやろうと思って企画をしていて。その展示の中で、基礎研究が大事だと言う方もいらっしゃるし、臨床応用が大事で、人の病気を治療するという研究もあって、その両方が大切ですよというふうに伝えていきたいときに、研究者が200人ずついる、100人ずついるっていうときに、その研究テーマを、面積の半分ずつ使うのか、はたまた臨床応用で治療に資する研究のほうが大事だよと思って、面積を90対10にするのかによって印象が変わりますよね。そういうのをどうバランス良く伝えるかというのは博物館としてはすごく重要だなと思うし、それを順番に並べるのか、面積として区分けしてしまって、大きく左は基礎研究、右は臨床研究というふうに分けるのかだと、来館者の体感の仕方が変わってくるので、そこを上手く伝えることができれば、いわゆるオンライン上のキュレーティングとは少し差別化ができるかなとは思っているんですけどね。
空間メディアとしての博物館
若原 なるほど。空間メディアとしての博物館の特長を上手く捉えて、ものを並べたりおすすめしたり、カテゴリー分けしたりということですね。
塩瀬 そうですね。キュレーティングの選択肢が増えるぐらいなのかもしれないんですけど。
若原 あともしこういうことが実現できたら面白いかなと思ったのが、博物館とか美術館に行く以外の日常、例えば買い物に行くとか、キャンプに行くとかっていう行動の中で、博物館、美術館内の閲覧行動以外の行動履歴から、この博物館のこういうものを見たら面白いと思うんじゃない?とか、こういう場所に行って、こういうの面白いと子どもが言っていたなら、子どもにこういうのを見せてあげたらいいんじゃない?とか、ほかの活動と上手く紐づけた展示のおすすめの仕方ってあり得たりするんですかね?
インクルーシブデザイン
塩瀬 そういう意味で言うと、これは動物園でやっていたプロジェクトなんですけど、動物園の中で、僕はインクルーシブデザインというプロジェクトをやっているんですけど、それは、目の見えない方や車椅子の方、高齢者やお子さんのような、普段システムとかサービスを作るときのメインターゲットにならなさそうな方を中心プレイヤーにして、一緒にサービスとかを体験しながらデザインしていくというものなんです。例えば動物園を目の見えない人と一緒に回ったとき、シマウマをどうやって言葉で説明するかとか、小さな子どもにキリンの餌の食べ方をどうやって教えるかとか、そういうのをそれぞれの人の見方を視点として提供するというのを、教材メーカーさんと一緒に作ったんです。
動物のかかとだけ見て回る
塩瀬 例えば動物のかかとだけ見て回るとか。そうすると、キリンのかかとはどこにあるんだ?っていうふうに見ると、みんなが思っている以上に結構上にあったりとか。
若原 そもそもどこにあるのか、みたいな話から始まるんですね。
塩瀬 キリンとかクマは、人間の手で言うと中指立ちをしていたり、2本指立ちをしていたりするので、かかと部分はもっと上にあると。レッサーパンダはかかとを地面につけて歩いてるんですね。かかとを地面につけて歩く動物って、立とうと思えば立てるんですよね。だからレッサーパンダが二足歩行したってみんなで喜んでいるのは、動物園の人からすると普通なんです。ワイドショーのネタになったりするけど。かかとがつく動物と言ったら、ほかにもクマはかかとをついて歩いているので、クマも立てますよね。そういうふうにかかとだけ注目するとか。あとはモグモグする口の形。モグモグ、ヒクヒクだけ見て回るとかっていうのを注目するのが上手な子の見方をほかの人たちに提供すると、周りの人たちも、ヒクヒクとピクピクだけ見て歩くってやると、シマウマとかは耳をピクピクさせるんですよね。で、クマは鼻をヒクヒクさせるんですよね。それは何かというと、敵とか獲物とかを探すときに自分のどの感覚を使うかといったとき、耳を使う動物は耳で敵を見つけるし、鼻を使っている動物は鼻で探すので、クマとかはイヌよりも何百倍も鼻がよかったりするので、そういうのがわかるきっかけになると。
目線の違いを視点に
塩瀬 キュレーティングのとき、獣医さん目線とか、飼育員さん目線とか、ほかのやたら動物にかじりついて見ている子の目線とか、そういう意味でさっき言ったタクソノミー的な、専門家による分類の面白さもあれば、フォークソノミー的な、変にこだわっている、動物好きな人の目線って、どちらも楽しめると思うので。
今までオフラインだった場合は、専門家の人しか分類事業になかなか携われないので、オンラインになっていろんな人がアクセスできると、有象無象の素人考えもたくさんあふれしまって質が悪くなるという言い方もされると思うんですけど、その中にはもちろんキラッと光るものもあって、時に専門家を越えるような目線もあって。確率は減ると思うんですよね、専門家を訓練施設を育て上げていった結果集めたものに比べると。だから打率の問題になって、ホームランを手に入れるようなオンライン的なキュレーティングもあれば、ヒットをたくさん重ねる専門家集団によるキュレーティングもあるのかなと。その両方を今享受できると考えれば面白い時代なんだろうし。
若原 それって展示みたいな分野にとどまらない考え方になるんじゃないかなと思いますね。
塩瀬 そうですね。みんな一緒なんじゃないかなと個人的には思うんですけど。
若原 スポーツ観戦とかも似たような感じありますよね。
塩瀬 まさにそうだと思います。
若原 ライブで見れる熱気の良さもあれば、今マルチアングルみたいな見え方で、テレビで見るほうがアップを見れたり、引いて見れたり、いろんなところから見れて、それぞれの面白さがあるという世界って、結構いろんな場所でありそうですね。
バーチャルリアリティの没入感と「どこを見せるか」
塩瀬 そうですね。僕も大学院の頃、バーチャルリアリティの研究をしていたんですけど、バーチャルリアリティは没入感が重要になるので、今から20年前とかだとレンダリングとか、コンピュータ上に背景を設置するとかっていうのも今ほど計算速度の速いパソコンは安くなかったので、いかに計算コストを下げてきれいに見せるか、というところに終始していたんですよね。でも結局没入感って大事だなと思ったのは、自分が見たいところを見れるというのが重要で、画質の良さよりもどこを見せるかというほうが重要だなとそのとき思ったんですね。
シュートシーンだけじゃないサッカーの見方
塩瀬 そうすると、例えばサッカーの観戦とかで、日本の番組にすごく多かったなと思うのは、シュートシーンばかりがダイジェストで流れてきていると。僕もサッカーをずっとしていたので、サッカーをしていると、そこじゃないところを見たいというのがたくさんあるんですよね。学会とかでヨーロッパに行ったとき、夜中テレビ見ているとユーロスポーツという番組がやっていて、そこでユーロとかヨーロッパの大会の放送をしていたとき、ディフェンダーがカットした瞬間とか、スローインの瞬間からリプレイが始まるんですよね。このディレクターはめっちゃサッカー知っているんだろうなと。この人わかっているなと。そこからリプレイしてくれるんだ、というのがあったとき、その見方がほしい!というのがあったら、ライブ会場だと自分で選べるじゃないですか。そこが多分臨場感の一つで、みんながわーっと言うタイミングと、そこまでの盛り上がり、入りそうで入らないところに対してのググーッという溜めみたいなものを空間で感じられるんだけど、テレビではそこは感じにくいと思うんですよね。
去年NHKの4Kシンポジウムがあったとき、4K、8Kに関しての使い方で、僕もパネルでしゃべらせていただいたんですけど、4Kと8Kをそのまま放送するのは、まだ受容する媒体としてのテレビが出回っていないので、そのままで見れないと思うんですよね。僕はどちらかというと、4KよりもHDサイズの、画面サイズで言うと16分の1とか、4分の1のサイズの画面に、そのまま4Kと8Kの映像を放送したらいいんじゃないかなと思っていて。そうすると、4Kの映像の中に今のハイビジョンクラスだと4枚映像がとれるんですよね。8Kだとさらにその16倍とれるので、そこから1枚自分で好きなところを選んで見れるようにしたら、サッカーでも、キーパーだけずっと見ている人とか、審判だけずっと追いかけるとか、自分の見たいところが見れるようになるのかなと。
視点の選択可能性/双方向のメディア利用
塩瀬 その視点の選択可能性みたいなところは、没入感とか、それに対するライブ性を得るための一つの手段だと思うので、もう少し視聴者側が選択できるというのを増やせると、情報提供の仕方もガラッと変わるんじゃないかなと。監督とかカメラマンが世界を切り取るわけですよね。本当はカメラマンができるだけ押さえて、そこから監督、ディレクターが画角を絞って、番組で編成して届けるっていうのが、究極の一方通行の捉え方で。でも、360度カメラで映像として、動物園とかサハラ砂漠を撮って、そこから見たいところだけを視聴者が編集できるようになると、好きなところを見れるというのはいいかなと。でも全員が全員自分で選べるわけじゃないので、その中でもキュレーターとしてリードしていく素人が増えてくるのかなと思います。そういうのができると、みんながみんなで新しい価値を生み出しながら、享受できるという本当の双方向のメディア利用ができるのかなと。
若原 面白いですね。そう考えると、美術館とか博物館みたいな場所のあり方というか、僕らの生活の中でも関わり方がだいぶ変わりそうな感じがしますね。
最後までお読みいただきありがとうございます。
第2回は以上です。いかがでしたか?
塩瀬さんとの対談の続きは、最終回「ミニフューチャーシティ」データドリブン社会が機能するためのヒント (ゲスト : 塩瀬隆之さん第3回) へ続きます。