ビジネスを変革する顧客データ活用法 Vol.3
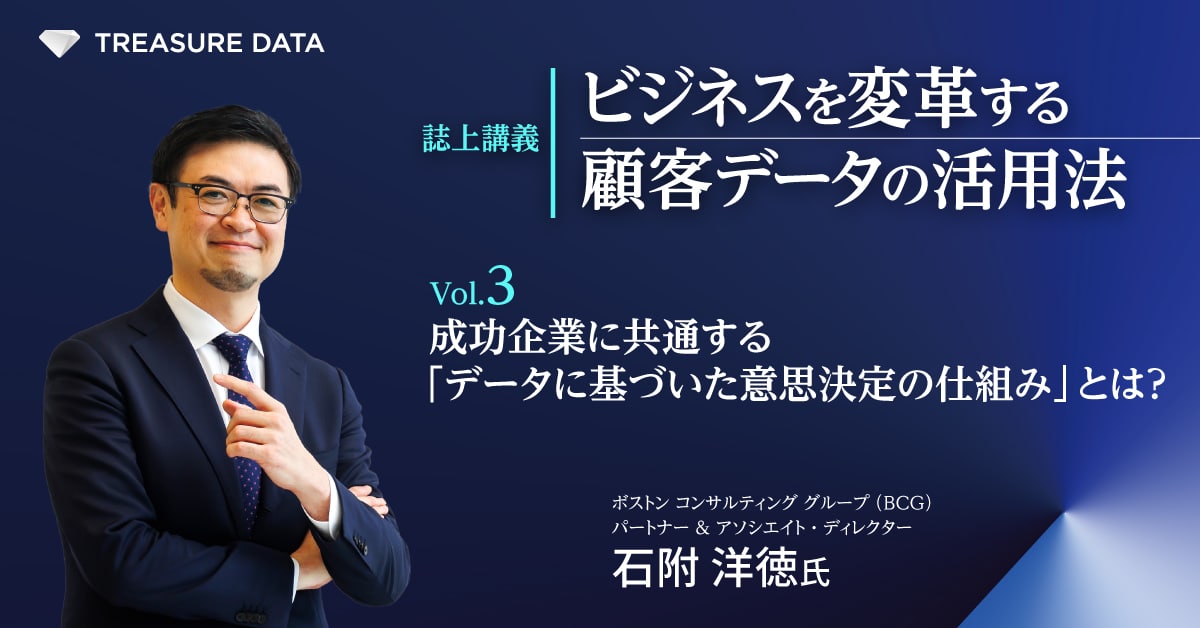
顧客データをいかにビジネスに活用するか。これは、多くの企業にとって重要なテーマと言えるだろう。顧客データの活用は、企業が顧客中心のビジネスモデルを構築するための基盤となる。顧客の声を聞き、それに応じて製品やサービスを改善し、新しい顧客体験を創出することで、企業は顧客の期待を超える価値を提供し、不透明な市場環境の中でも持続的な成長を達成することも可能だ。ただし、その実現は言葉で言うほど簡単なことではない。顧客データの活用に詳しいボストン コンサルティング グループ(BCG)の石附 洋徳氏が5回にわたり、活用のポイントや注意点について解説する。
Vol.3
成功企業に共通する
「データに基づいた意思決定の仕組み」とは?
CX(Customer Experience:顧客体験価値)やLTV(Life Time Value:顧客生涯価値)の向上は、社内の全部門が横断的に取り組まなければ実現することは難しい。その際の部門間の「共通言語」となるのがデータである。CXやLTV向上に成功している企業はほとんど例外なくデータに基づいて考え、意思を決定するプロセスを定着させている。そうした文化を培うには、データ分析で課題を解決する成功体験を積み重ねるとともに、現場の社員から経営層まで全社員がデータ活用の意義を深く理解することが重要だ。
<目次>

データを「共通言語」に社内の連携を図る
この誌上講義のVol.1「なぜ LTVの向上が企業成長の鍵となるのか?」では、CS(Customer Satisfaction:顧客満足度)ではなくCXをビジネスの軸とすることの重要性に触れました。UI(ユーザーインターフェース)やUX(ユーザーエクスペリエンス)など似た概念はほかにもいろいろありますが、CXはそれらの中で最上位に位置し、その企業の存在意義である「パーパス」とも重なる部分が多いものだと思います。
パーパスに基づく自社の提供価値をしっかり認識し、そのときどきで「点」としてCSを満たすのではなく、「線」や「面」としてカスタマージャーニー全体の質を引き上げられれば、LTVもおのずと高まるでしょう。
ただしそのためには、事業展開においてCXの向上を常に念頭に置き、そのための効果的な施策を展開しようとする姿勢が、マーケティング部門に限らず全社員に定着していなければなりません。自社が提供したい価値と照らしあわせた際に、「商品やサービスがどうあるべきか」が明確になれば、それを顧客に届けるためにどのようなサプライチェーンを構築しなければならないかも見えてきます。これは各部門が連携して取り組むことによって実現するもので、足並みがバラバラでは齟齬が生じてパーパスと合致した価値提供はできません。
社員や部門が連携する際に「共通言語」となるのはデータです。成功している企業を見渡すと、ほぼ例外なくデータによって意思疎通をし、あらゆる物事をデータを基に捉える文化が根づいています。しかし、マーケティング部門やデータ部門などが顧客データを分析して得た発見に基づいて業務の最適化を促しても、肝心の現場担当者の理解・共感を容易に得られない――そんな悩みを抱える企業が少なくありません。
どの部門も長年の経験の中で最適化されてきたプロセスで業務をしていますし、抱えている課題にもそれなりの理由があるものです。そこが理解されないままデータだけに立脚した“正論”を示されても、受け入れる気になれないのも無理はありません。また、提示されたデータが現場の感覚と異なっていれば、「データ上はそうかもしれないが、このやり方でうまくやっている」で終わってしまうパターンもよくあります。
そうした事態に陥るのを防いで、現場にデータの有用性を理解してもらうにはどうすればよいのでしょうか。効果的な方法は、「現場の誰もが感じているちょっとした困りごとをデータ分析から導いた解決策で解消して、成功体験を共有すること」です。
課題解決の突破口をデータに見出す
私がかかわったある企業は、アプリユーザーの離脱率がにわかに高まったにもかかわらず、その原因を特定できずにいました。そんな状況を突破する糸口となったのが、ほかならぬデータ分析です。
そのアプリには、ユーザーの行動データを収集するツールが入れられていました。これらのデータを多角的に解析することで、多くの離脱者がたどる行動パターンや、途中まで離脱パターンをたどりながらも回避した人の動きが手に取るように分かり、それに基づく改善案が各部門の担当者から次々に出されたのです。地理情報システムで取得したジオデータもあり、シチュエーションごとのユーザーの行動特性を分析できたことも大いに役立ちました。
結果的にユーザーの離脱を食い止めたその企業は、現場担当者から役員クラスに至るまで、顧客データを分析することの重要性を痛感。それを機に、あらゆる局面でデータを軸として目の前の状況を把握しようとする姿勢が全社に定着しました。
別のある企業では、Webサイト上でのユーザーの行動を収集・分析するツールが導入されていたにもかかわらず、ツール操作に慣れていないといった理由で、大半の社員が積極的に使おうとはしませんでした。そこでその分析ツールの使い方や、ユーザー操作のデータを分析することの意義を解説する研修会を開くとともに、分析ツールの利用をサポートする体制や仕組みを整えたところ、データ分析とはまったく無縁だった多くの社員が顧客のニーズや動向の把握に積極的に利用するようになり、それまで見過ごしていたインサイトに気づけるようになりました。
この会社の営業部門では、自社商品に興味を持ってWebサイトを訪れたユーザーが購入に至らなかったケースを分析して有効な対策を立案。また、商品開発部門は自社のコアなファンがどんなサービスを求めているのかを多面的に把握して新しいサービスの開発に役立てています。
成功体験を共有しデータ分析の大切さを多くの社員が実感してから環境を整えるのか、逆に全社員が手軽にアクセスできる環境を用意してからデータを活用する文化を醸成するのかは、企業によってケースバイケースでしょう。いずれにしてもデータに立脚して思考する土壌が社内に形成されると、現場の課題解決や業務の改善を通じてCXが高まるだけではなく、データ分析から導き出されたKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)が経営資料に盛り込まれ、「来年度はこのスコアを何%上げます」といった提案がなされるなど、組織のレベルが一段アップすることも望めます。
メーカーであればデータから正確な需要予測をし、調達を適正化してサプライチェーンを改善するといったことも可能です。このように、データ活用は事業プロセスを変革させるほど大きな力を秘めた「成長エンジン」といえます。
デジタルネイティブ世代によるデータ活用の推進力
データ活用の機運を盛り上げるために目を向けたいのが、ITリテラシーが比較的高いデジタルネイティブ世代の若手社員です。一人ひとりのニーズに合わせた商品やサービスを提案するパーソナライゼーションを当たり前のものとして受け止めている彼らには、データ活用に対するハードルが上の世代ほど高くありません。
むしろ機会があれば積極的にデータを活用したいと考える人が多く、その背景には、データ分析で得られる収穫を、実際の経験から知見を積み上げてきたベテラン社員とは異なる“武器”にしたいという思いがあるような気がします。彼らは、データという裏付けによって提案の説得力が増すことを感じているのでしょう。
若手社員に推進力になってもらうことは重要ですが、一方で経営層もまた、データ活用の意義を十分に理解しなければなりません。経営とは本来データを基軸に行われるものであるはずですが、ベテラン社員の経験や勘に重きを置きがちな日本企業も多いのが現状です。もちろんそうした要素も大切ではありますが、それに頼りすぎず、データから得られる気づきや発見も同等に経営判断の材料とするべきです。
経営層がリアルタイムに経営状況を把握できる環境を構築しようとすれば、各現場はトップに報告する「共通言語」としてデータを整えることになります。そうすればやがて現場とトップだけではなく、組織全体がデータを媒介にコミュニケーションを図れるようになるでしょう。
部門間のデータサイロ化問題とその解決策
データを社内の共通言語とするうえでの大きな障壁は、蓄積された業務データが特定の部門に閉じられてしまうことです。例えば営業部門がSFA(Sales Force Automation:営業支援)やCRM(Customer Relationship Management:顧客管理)ツールを使っていても、そのデータが営業部門内にサイロ化して置かれていたのでは、せっかくの有用な情報を他部門の社員が活用することはできません。
その問題を解消する手段が、これまでにも何度か触れたCDP(カスタマーデータプラットフォーム)です。その最大のメリットは、複数の部門に散在する顧客データが一元化され、社内の誰もが速やかにアクセスできるようになること。Webサイトやアプリ、実店舗などのタッチポイントごとに保管されているデータを個別に分析していたのでは、一人ひとりの顧客がどんな生活背景を持ち、どのようなプロセスで商品を購入しているのかといった全体像を把握することはできません。
しかしそれらのデータをCDPに集約すれば、一人の顧客に関するすべてのデータを単一のIDで管理・分析できるようになります。また、CDPをメルマガやデジタル広告配信の仕組みなどの広告システムと連携させれば、データ分析によってパーソナライズされたさまざまな情報を、適切なタイミングで発信することも容易になります。パーソナライゼーションが今後のマーケティングにおいてますます重要性を帯びることは間違いなく、その意味でもCDPが果たす役割はさらに増大しそうです。
こうした状況からCDPを導入する企業が急増していますが、「データの可視化」をゴールに設定してしまったのでは、思うような成果は得られません。各業務部門がそれを的確に分析して得た知見や気づきを経営判断に反映させる流れが整って、初めて有効に機能するからです。

ボストン コンサルティング グループ(BCG)では、CDPを整備しようとする企業に対して、単にソリューションを導入するだけではなく、データ活用に向けた社内の意識改革も含めたトータルサポートを提供しています。
「データ環境のインフラ整備」「各業務現場でのデータ分析の実践」「経営層の意思決定プロセスの適正化」。企業を成長させるデータ活用は、これらが一体となって行われて実現するものだということを念頭に置くことが重要です。
第1回:なぜLTVの向上が企業成長の鍵となるのか?
第2回:今、あらためて考える 顧客データ活用の重要性と可能性とは?
【次回】第4回:AIが実現するマーケティング革命ハイパー・パーソナライゼーションと効率化の可能性とは?
<スピーカー>

石附 洋徳 氏
ボストン コンサルティング グループ(BCG)
パートナー & アソシエイト・ディレクター
博報堂、カシオ計算機でCDO兼CIOを務め、2023年にBCGに入社。マーケティング・営業・プライシンググループのコアメンバーで、デジタル・マーケティング、EC、CRMのエキスパート。マーケティング領域でのデータやデジタル技術を活用した事業変革、新規サービス開発などを得意とする。また、製品開発、サプライチェーン・マネジメント(SCM)、インフラ、セキュリティに至るまで幅広い領域でのデジタルトランスフォーメーションの経験が豊富。











